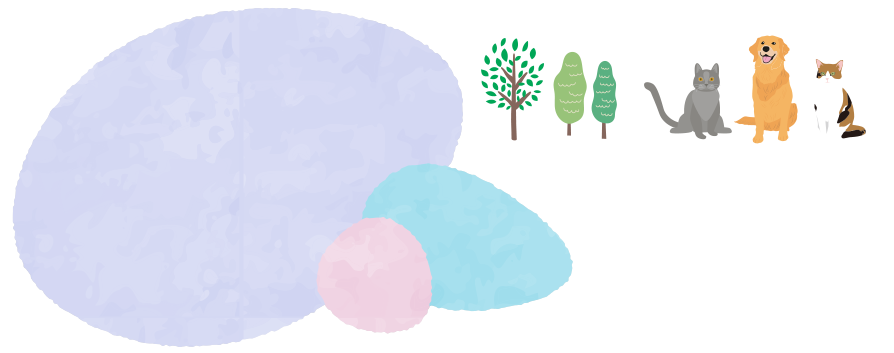
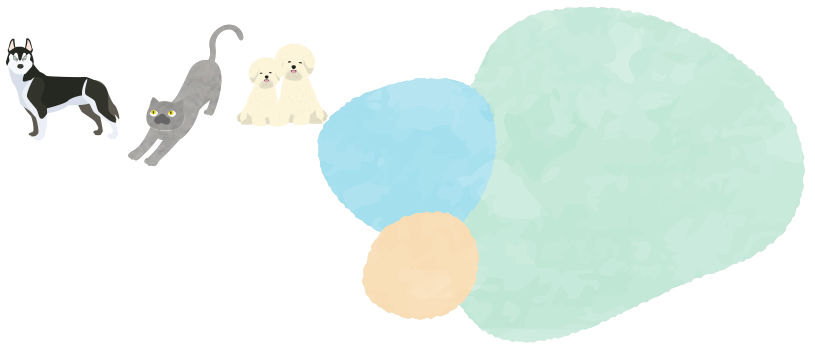

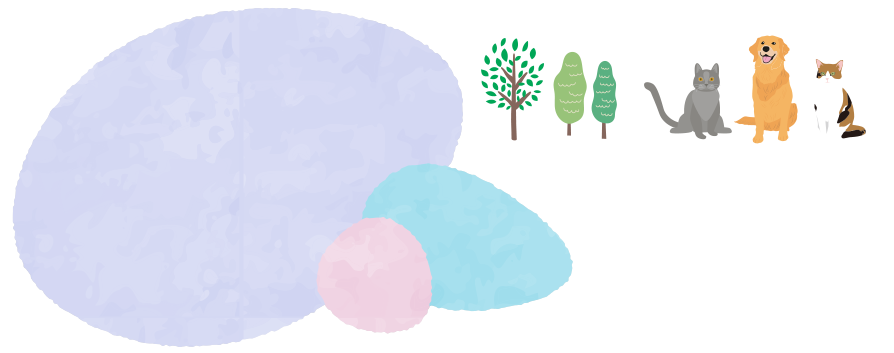
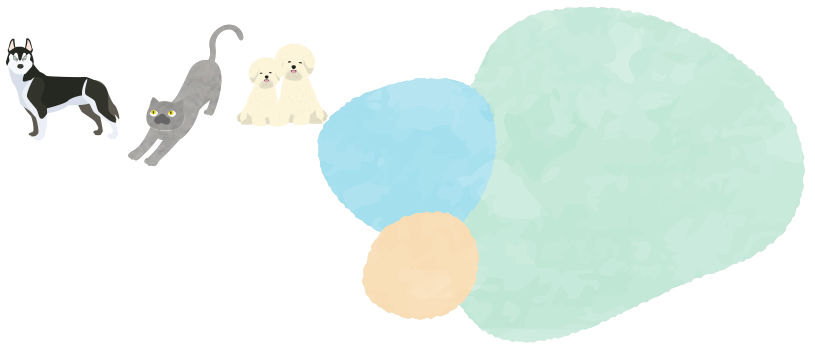

こうご動物病院の循環器科について掲載しています。
![]()
・咳が出る
・呼吸が荒くなりやすい
・疲れやすい(散歩が短くなった、運動を嫌がる)
■僧帽弁閉鎖不全症
僧帽弁閉鎖不全症とは犬の心臓病で最も多い進行性の心臓病です。
特に高齢の小型犬に多く、聴診器で聞こえる心雑音のほとんどの原因が僧帽弁閉鎖不全症です。
犬と猫の心臓は4つの部屋に分かれており、心臓内の血液の流れる方向が決まっています。この血流を一定方向にする働きをもつ「弁」が存在し、しっかりと閉じることで逆流を防いでいます。しかし、加齢や遺伝の影響でこの「弁」に変性が起こると、心臓内に逆流が生じ、その逆流が心雑音として聞こえます。
血液が逆流してきた部屋には圧がかかり、心臓の筋肉を内側から押し広げるため「心拡大」がおこります。
心臓が大きくなると呼吸が荒くなったり咳が出たり、血流が悪くなって疲れやすくなったり動きたがらなくなったり、進行すると肺に水が溜まってしまう肺水腫という病態を引き起こすこともあります。
命に関わる病気で、基本的に治ることのない病気のため、病気のステージと症状に合った検査と投薬が生涯必要となります。外科手術が適応となる場合もあります。
■肥大型心筋症
肥大型心筋症とは猫の心臓病で最も多く、症状や心雑音が全くなくても約1割の猫が罹患しているといわれている病気です。
生後数か月から高齢までどの年齢でもなり得ますが、特に大型種の猫に見られます。
心臓は全てが筋肉でできており「収縮」と「弛緩」を繰り返す事で血液を全身に送ります。その心臓の筋肉(=心筋)のタンパク質に異常が起こる事で「収縮」と「弛緩」の働きがしっかりとできなくなり、心臓の壁が厚くなることで心臓の拡張機能が低下します。
重篤化すると、うっ血に伴う左心不全を発症し、血栓塞栓症につながる可能性があります。
血栓が詰まった血管の先には血液が流れなくなるため、神経が障害され、激しい痛みが生じます。腹部の大血管に血栓が詰まることが多いため、異常な痛みや急性の後肢麻痺が見られることが多いです。生存率が低い疾患なので、症状を見つけたらいかに早く治療をスタートできるかがカギになります。
命に関わる病気で、治ることのない病気のため、病気のステージと症状に合った検査と投薬が生涯必要となります。
①問診
まずはしっかり問診させて頂きます。
咳や呼吸状態を確認し、いつごろからの症状なのかなどをお伺いします。
②検査
一般身体検査、血液検査、レントゲン検査、超音波検査を行い、治療前の心臓の評価をします。
また他臓器にも影響が出ていないか、合わせて確認をします。
③内科療法の場合
心臓の評価と症状を照らし合わせ、投薬治療が開始となります。
心臓以外に異常が出ている場合も合わせて治療が必要です。
生涯にわたって薬が必要なため、飼い主様の時間や費用的な問題もご相談させていただきます。
④外科療法の場合
僧帽弁閉鎖不全症の場合、外科手術にて弁の治療をすることが出来ます。
患者様の病態や飼い主様のご希望によっては外科手術を検討する場合もあります。
外科的な治療には専門の設備が必要とされるため、手術ができる病院は限られています。
ご希望の飼い主様には循環器専門の病院をご紹介いたします。
⑤定期的なモニタリング
投薬を開始して終了ではありません。
薬を開始して調子が良くなっても、ゆっくりと病態は進行していきますので定期的な心臓の評価が必要です。
治療していても急激に悪化する場合もありますので、体調の変化があれば些細なことでも大丈夫ですので早期にご相談ください。
循環器疾患の場合、基本的には、投薬での治療がメインとなります。
心臓病の初期で投薬治療がまだ推奨されないレベルの異常が見つかったとき、飼い主さんの希望があれば、相談の上、漢方やドイツの自然療法(ホモトキシコロジー)の内服をスタートして定期検査をすることもあります。なるべく心臓病の進行を防ぎたいという場合には、お気軽にご相談ください。