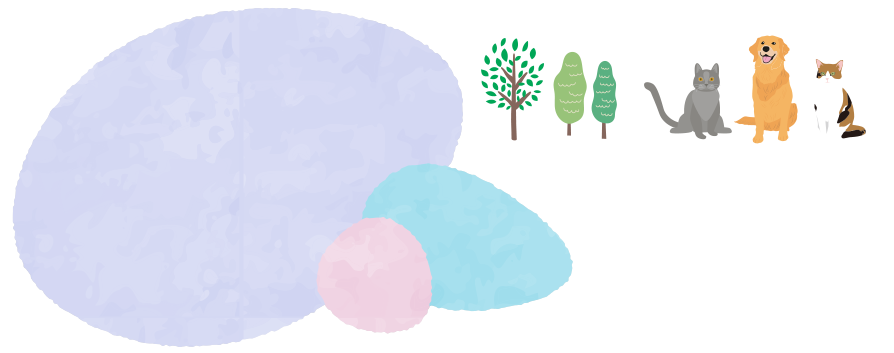
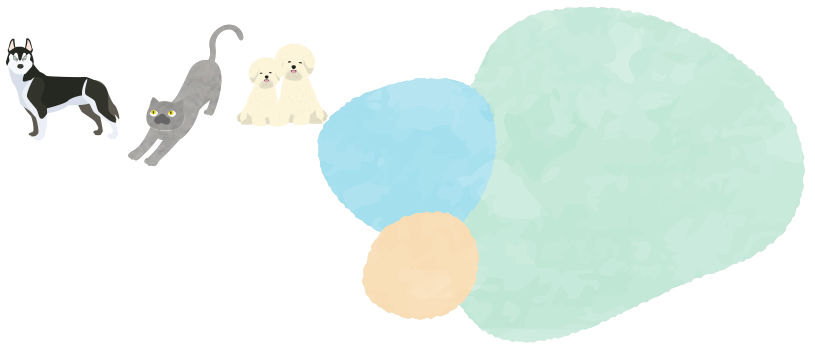

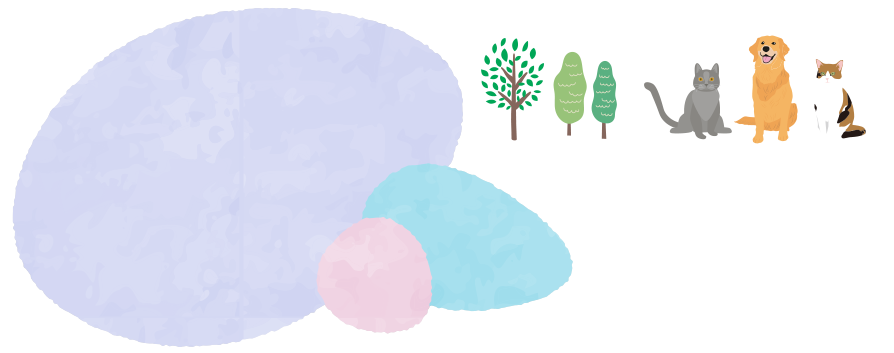
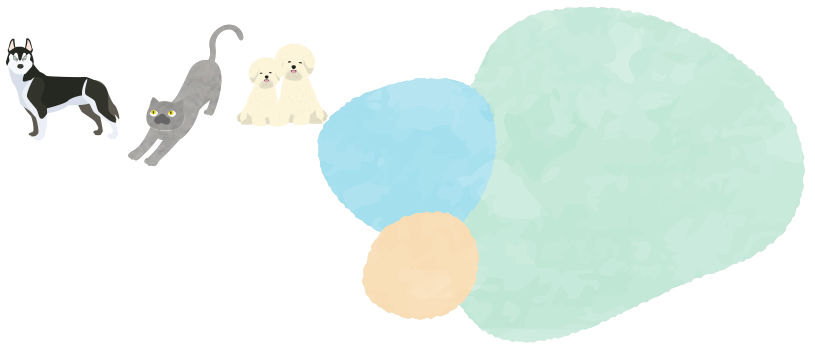

こうご動物病院の皮膚科について掲載しています。
![]()
・痒みや赤みがある
・かさぶたが出来やすい
・身体や足先をよく舐めている
・脱毛やフケ、ベタつきがある
・シャンプーをしてもすぐに臭う
・皮膚が腫れてきている
■食物アレルギー
食物アレルギーは主に1歳未満もしくは7歳以上で好発するとされています。口まわり、眼の周り、耳、腰、肛門周囲など様々な場所に痒みと赤みが出てきます。食物アレルギーは痒みが強くなる傾向があり、他の皮膚病で用いる量の痒み止めを使っても十分に痒みのコントロールができないこともあります。
食物アレルギーの原因はその名の通り、「食物」ですから食べているもの(特にタンパク源)を見直す必要があります。この時に大事なのはフードだけでなく自宅であげているおやつ(ささみやジャーキーなど)、予防薬、デンタルガムまで口に入れるもの全てを見直しの候補に入れることです。アレルギー検査を用いて、痒みの原因のタンパク源を特定したり、食事を変更または制限することで治療していきます。
■アトピー性皮膚炎
犬アトピー性皮膚炎は遺伝的素因を背景とした慢性の痒みを症状とする皮膚病です。症例の多くは環境アレルゲンに対する抗体を持つだけでなく、ドライスキンなどの皮膚バリア機能の低下を招く体質を持っています。そのため、完治させることが困難であり、いかにうまく痒みをコントロールして病気とお付き合いしていくことができるかを考えてあげる必要があります。痒みを抑える内服薬や塗り薬、シャンプーなどのスキンケアを併用してトータルで治療をしていきます。
■膿皮症
膿皮症の原因は体表の常在菌(病気じゃなくても存在する菌のこと)が皮膚バリア機能の異常によって過剰に繁殖してしまい表皮や毛包に感染する事で起こります。夏場は気温上昇に伴って細菌の活動が活発になり頻発します。主に抗生剤やシャンプー療法での治療となりますが、再発を繰り返す時は基礎疾患(ホルモン病など)が隠れている事が多いので合わせて治療が必要となります。
全犬種に起こり得る病気で、夏場になりやすい傾向があります。
■マラセチア性皮膚炎
マラセチアは皮膚の常在菌の一種で、皮脂をエサにして増える酵母菌です。皮脂の分泌が多く、皮膚がベタベタしているほどマラセチアにとっては増えやすい環境になります。マラセチアが分泌する脂肪分解酵素や皮脂の分解により生じた脂肪酸が皮膚に浸透し炎症を起こさせることで、マラセチア皮膚炎になります。
マラセチアが増殖する原因は、過剰な皮脂の分泌(脂漏症)、角化異常症、アレルギー性皮膚疾患、内分泌疾患、栄養不良、高温多湿の環境などが考えられています。アレルギーや内分泌疾患が原因となる場合はそれぞれの疾患にあった治療が必要となりますが、幼い頃から脂っぽく、マラセチア皮膚炎を繰り返している場合は本来の体質としての脂漏症を疑います。その場合は、生涯にわたり頻回のシャンプーや細やかなスキンケアが重要となってきます。
■脂漏症
脂漏症はフケやベタつきを主な症状とする皮膚病です。生まれつきの体質である先天性の脂漏症と他の病気(内分泌異常、アレルギー、免疫異常など)が影響して起こる後天性の脂漏症があります。シャンプーや保湿剤といったスキンケアを中心に治療を行う必要があります。また、痒みを伴う場合は内服薬を併用することもあります。
■ノミアレルギー性皮膚炎
このアレルギーはノミの唾液内の抗原に対する過敏反応により発症します。アレルギーが成立している猫では、少数のノミの寄生・刺咬でも全身に重度の皮膚症状を起こすことがあります。一方、アレルギーが成立していない猫では多数のノミに寄生されていても、たいした皮膚症状は起こしません。そのため、「ノミアレルギー性皮膚炎」と「ノミの寄生」は分けて考える必要があります。ノミアレルギー性皮膚炎の治療のポイントはとにかく、「ノミに刺されないこと」です。定期的にノミの駆虫を行い、ノミがいるところへは出さないようにしましょう。またノミから回避できても数週間はアレルギー反応が続くことがありますので、その時は痒み止めを併用することがあります。
■非ノミ非食物アレルギー性皮膚炎
猫では犬アトピー性皮膚炎のように診断基準や定義が確立していないため、このように呼ばれることが多いです。いわゆる「猫アトピー」と言われたりします。感染や寄生虫、ノミや食事によるアレルギーを検査で丁寧に除外していき、診断を行います。治療はステロイドや免疫抑制剤を用いて痒みのコントロールを行いますが、犬と比べると用量が多くなりやすいです。
■皮膚糸状菌症
皮膚や毛・皮脂腺などで増殖する皮膚糸状菌(カビ)によって引き起こされる病気です。猫の皮膚糸状菌症では痒みはあまり強くないことが多いですが、重症になると全身の毛が脱毛してしまう場合もあります。また、このカビは人間にもうつるため、人獣共通感染症としても重要な病気です。内服薬やシャンプーでの治療がメインとなりますが、猫の場合はシャンプーが苦手な事が多く外用薬での治療も行います。
感染している部分が多いときは全身の毛を刈ってしまうこともあります。あまり痒みはありませんが子猫や老猫では細菌などの二次感染も起こり治療期間が少し長くなる事もあります。
■心因性脱毛症
心因性脱毛症は過剰なグルーミングやひっかきにより引き起こされる自己傷害性の皮膚病です。原因として生活環境の変化や身体の異常からくる分離不安症などの精神的な背景が関与していると考えられていますが、原因が特定できないケースも多々あります。治療は環境の改善が第一となりますが、サプリメントやお薬を併用していく場合もあります。
①問診
どの症状が、いつから、どのように進行してきたかを細かく伺います。飼い主さんの何気ない言葉が診療のヒントになることもありますので、遠慮なくお話ししてください。皮膚以外の病気が原因となっていることもありますので、体調や普段の様子についても教えてください。
②検査
皮膚表面の細胞を取ったり、毛を抜いて毛根の状態を確認します。各種検査で特殊な皮膚病の可能性が出てきたときは局所麻酔を行い、皮膚の一部を取らせていただくこともあります。
また、アレルギーやホルモン性疾患が疑われる場合は血液検査が必要になることもあります。
③治療
痛みや痒みなど動物のQOLが下がるような症状がある場合、そこを一番に取り除くことを意識して治療をご提案しています。複数の治療のメリット・デメリットをご説明し、ご納得いただいた上で治療を勧めていきたいと考えています。治療を開始してすぐに改善がみられても、継続治療が必要な事もあります。改善がない場合は再度、皮膚の状態を評価し治療方法を変更する事もあります。元来すぐに治療の効果が出にくい疾患は、継続治療で経過観察となります。
④定期的なモニタリング
皮膚の状態が改善されて終了ではなく、今後のケアが再発を予防します。
再発したとしてもひどくなる前に対処する事で、治療期間の短縮と愛犬・愛猫のストレスの軽減につながります。
皮膚疾患の場合、食べているものが原因で起こる場合、一般的には処方食に変更することがあります。
しかし、処方食を食べてくれないコもいます。当院ではそういったコの場合、何が何でも処方食を食べてくださいというのではなく、そのコが食べれそうなもので治療への糸口を見つける手立てをします。具体的には、当院の付属施設である、癒しの杜にて食事のカウンセリングを専門の獣医師にやってもらい定期的に当院で症状のチェックをしていきます。
また食事とともに腸内環境の改善をすることで症状の緩和を導くことができることもあるので、そのコに合わせた腸内環境改善のサプリメントを併用することもあります。
しっかりとした薬用シャンプーを使って皮膚のケアをする必要がある場合、トリマーさんと相談して、そのコに合わせたシャンプーを使用して定期的に病院内でスキンケアをすることもあります。
皮膚疾患の場合、投薬治療が必要となることも多いのですが、なるべく薬を使用したくないという場合には、漢方やドイツの自然療法を利用することもあります。
いずれにせよ、皮膚疾患の場合には、生涯に渡る治療が必要となることが殆どですので、飼い主さんとしっかりお話しをさせていただき、どのような治療を希望されるのかによっていくつかの選択肢をお伝えして、相談の上、治療の選択をしております。