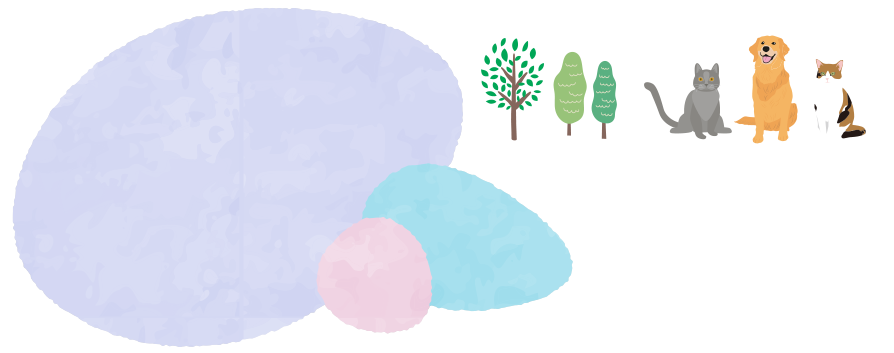
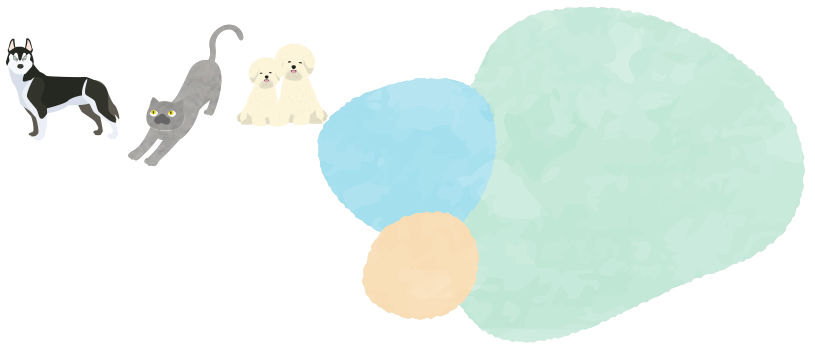

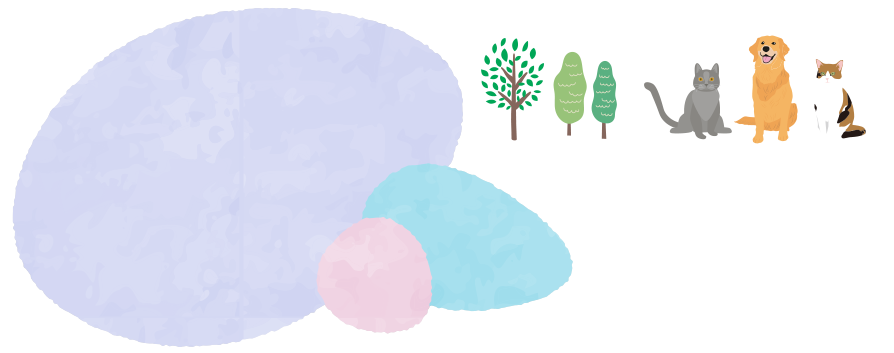
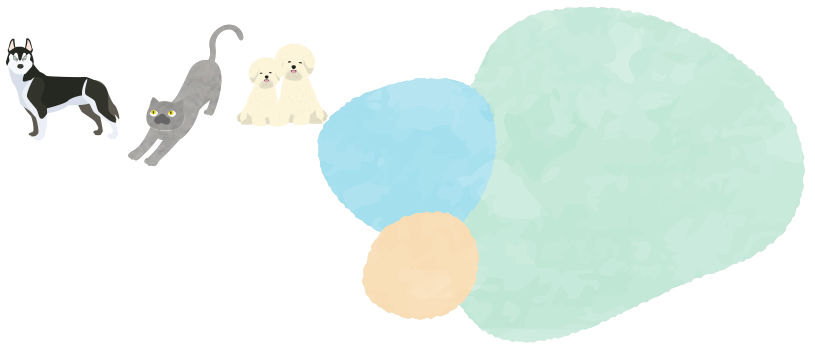

こうご動物病院の内分泌科について掲載しています。
![]()
・水を飲む量が増えた、おしっこの量が増えた
・食べる量は変わっていないのに体重が増えてきた
・全身的に毛が薄い
・お腹だけが張っている
・食欲があり食べているのに体重が減ってきた
・怒りやすくなった
■甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症は高齢の犬で多く見られる病気です。代表的な症状としては、対称性脱毛、尻尾の脱毛(ラットテイル)、ふけやべたつきなどの角化異常、体重の増加、活動性の低下などが挙げられます。診断は血液検査とホルモン検査で行います。治療は内服薬を用いることが多いですが、甲状腺の腫瘍が見つかった場合は外科手術が必要になることもあります。
■副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)
副腎から出るステロイドホルモンの量が過剰になることで起きる病気です。多飲多尿、多食、お腹のはり、脱毛、皮膚の萎縮、パンティング(常に息がハアハアしている)などの症状が見られます。血液検査、尿検査、超音波検査、特殊なホルモン検査を用いて診断を行います。治療の多くは内服薬で行いますが、副腎の腫瘍が見つかった場合は、外科手術による摘出を行います。
非常に難易度が高い手術であるため、当院では専門病院をご紹介しています。
■甲状腺機能亢進症
甲状腺機能亢進症は高齢(8歳以上)の猫ちゃんで多く見られる病気です。人のバセドウ病に近い病気です。甲状腺ホルモンの増加により、体重の減少、多食、多飲多尿、興奮、呼吸促迫、怒りっぽくなるなどの症状が見られます。診断は血液検査で行います。治療は内服薬を用いることが多く、甲状腺の機能を抑制する薬を飲む必要があります。また、高血圧を併発しやすく、降圧剤が必要となる場合もあります。
■糖尿病
猫の糖尿病の多くは、人の2型糖尿病に似ていると考えられています。主な症状は多飲多尿、多食、体重減少です。尿中の糖が増加することで、菌の養分が増え尿路感染が起きやすくなります。治療はインスリンの注射を行うことと、低炭水化物食を与えることが重要です。2型糖尿病は膵臓のインスリン分泌能が残っていることが多く、インスリン療法により状態が改善するとインスリン投与が必要なくなる場合もあります。
①問診
どの症状が、いつから、どのように進行してきたかを細かく伺います。特に体重の増減や水を飲む量、尿の量は変化が出やすいため、注意してお聞きするようにしています。
②検査
内分泌の病気で異常が出やすい部分の血液検査、尿検査を実施して、どのような可能性があるのかを調べます。その結果、疑いが強くなった場合は、超音波検査やホルモン検査を実施してより詳しく調べていきます。
③治療
内分泌の多くの病気では、内服薬により治療を行います。また、ホルモンを分泌する臓器自体が腫瘍化していることがあり、その場合は外科的に摘出することもあります。
外科的な治療には専門の設備が必要とされるため、手術ができる病院は限られています。ご希望の飼い主様には専門の病院をご紹介いたします。
糖尿病の場合はご自宅でのインスリン注射が必要になるので一緒に練習をして、お家で注射をしてもらっています。
④定期的なモニタリング
投薬を開始して終了ではありません。
安定したら数ヶ月おきの検査を続けることで定期チェックすることをおすすめ致します。
薬を開始して調子が良くなっても、体調や年齢の変化によってコントロール不良となることもあります。
体調の変化があれば些細なことでも大丈夫ですので早期にご相談ください。
内分泌疾患の場合、基本的には、投薬治療や糖尿病の場合はインスリンの注射を使って治療することが基本となります。
猫の糖尿病の場合は、症状が良くなりインスリン注射が必要なくなることはありますが、その他の内分泌疾患の場合、投薬を無くすということは基本的に難しいです。なるべく薬を減らしたいという相談をされることも多いので、その場合、ドイツの自然療法を併用することで症状によっては薬を減らすことも可能です。
いずれにせよ、内分泌疾患の場合には、生涯に渡る治療が必要となることが殆どですので、飼い主さんとしっかりお話しをさせていただき、どのような治療を希望されるのかによっていくつかの選択肢をお伝えして、相談の上、治療の選択をしております。