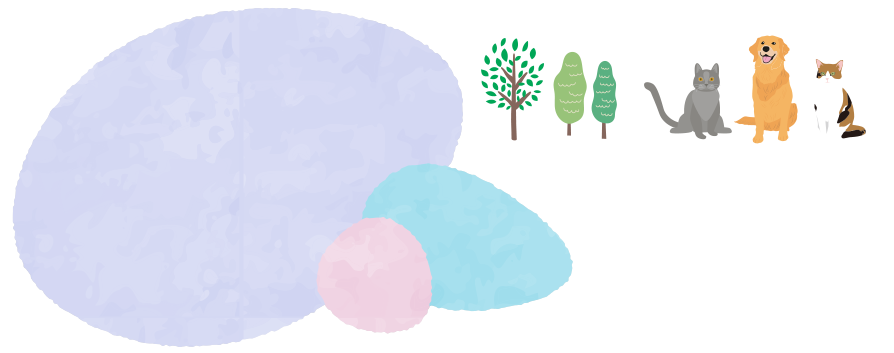
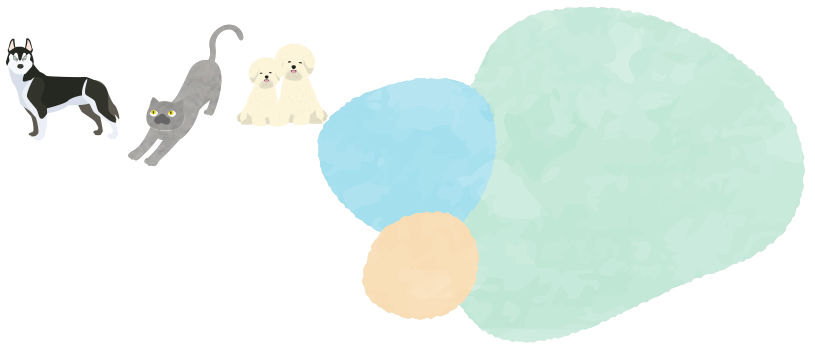

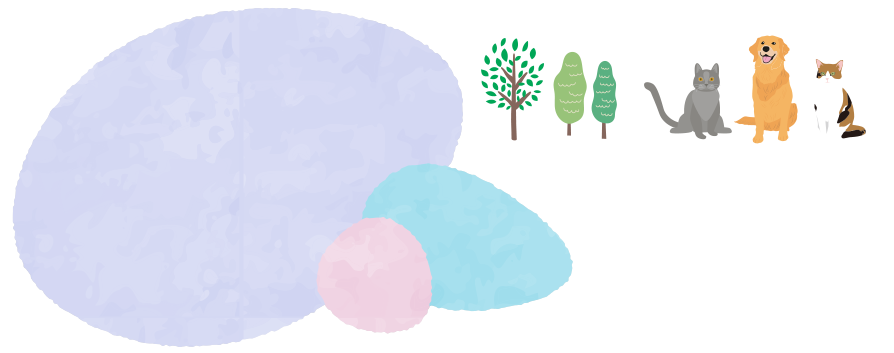
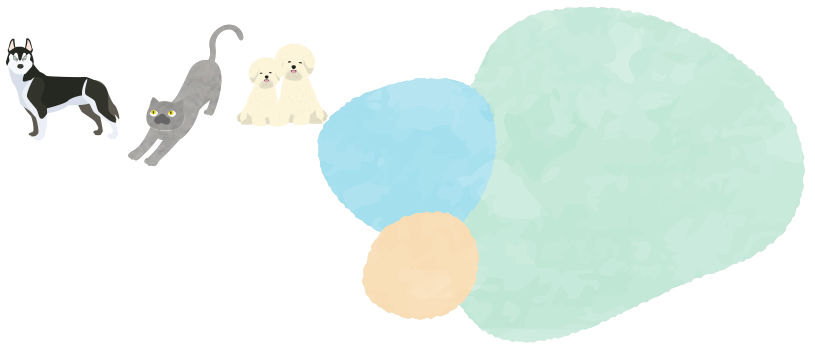

こうご動物病院の消化器科について掲載しています。
![]()
・よく吐く
・下痢を繰り返す
・血便や黒い便が出る
・食欲が減る
・体重が減る
■感染性胃腸炎
感染性の腸炎は細菌やウイルス、寄生虫などが消化管で異常繁殖して胃や腸の中で毒素を作り出し、下痢や嘔吐を引き起こします。
正常な消化管内は善玉菌と悪玉菌がバランスを保っていますが、細菌性の下痢を引き起こしている消化管内ではこのバランスが崩れています。主な感染経路は経口感染です。
下痢や嘔吐は食欲不振や脱水症状を示すため「何が感染しているか」を特定し、原因に合った投薬と症状に合わせた処置が必要となります。
■消化管腫瘍
消化管腫瘍とは胃や腸に発生する腫瘍のことをいいます。犬ではリンパ腫や腺癌が、猫では肥満細胞腫やリンパ腫、腺癌の発生が多く、いずれも高齢の動物に多くみられます。腫瘍の種類やどこに腫瘍ができているのかなどによって症状は若干異なりますが、主な症状は嘔吐や下痢、血便、食欲不振、体重減少などです。また、大きくなった腫瘍が消化管を塞いでしまったり、消化管に穴が空いて腹膜炎を起こしてしまったりすることもあります。その場合、緊急手術が必要になったり、命を落としてしまうことも少なくありません。
消化管腫瘍に対しては一般的には外科手術や抗がん剤治療が行われます。腫瘍の種類や進行具合を調べるために麻酔下でのCT画像検査が必要になることもあります。検査結果からどの治療法が適しているのか、リスクや体調を考慮してどういった治療を行っていくかを決めます。状況によっては積極的な検査や治療が難しい場合もあり、緩和治療を行うこともあります。飼い主様のご希望を伺いながら一緒にご相談させていただきます。
■異物誤食
布やひも、おもちゃなどを噛んでいる間に飲み込んでしまい、胃の出口や腸に詰まってしまうことがあります。食べたものが詰まった部分から先に進まなくなるため、頻回の嘔吐をするようになります。特にひも状のものが腸に詰まった場合、糸ノコギリと同じような作用で腸を引き裂いてしまうこともあります。治療は注射薬で嘔吐を誘発して吐かせる処置をするか、内視鏡で摘出するか、最悪の場合、お腹を開けて直接胃や腸から詰まっているものを取り除く外科手術が必要となることもあります。命に関わる場合も少なくありませんので、何か食べてしまった場合には早期にご相談ください。
■膵炎
膵炎は急な食欲不振や吐き気、下痢、腹部の痛みを症状とします。原因としては高脂肪食や分別なく食事を与えることが多いとされています。また、膵炎を起こしやすい犬種としてミニチュア・シュナウザーやヨークシャー・テリアが挙げられます。血液検査や超音波検査を行い、診断していきます。重度の膵炎の場合、炎症物質が全身に流れ、全身性の炎症反応を引き起こしてしまい、命を落とす事もある病気です。治療は炎症がおさまるまで点滴や吐き気止め、抗炎症薬を使用します。治療後の再発予防としてフードを低脂肪食に変更することが勧められています。
猫の膵炎は犬と比べると特徴的な症状が出にくく、元気や食欲がなくなるといったどの病気にも当てはまる症状しか見られないことが多いです。肝臓の疾患や糖尿病を発症した猫ちゃんの検査を進めていく上で偶発的に発見されるケースもあります。治療は犬と同様に点滴や対症療法を行います。
■食物アレルギー
食物アレルギーには皮膚症状と消化器症状があります。消化器症状としては嘔吐、下痢、排便回数の増加などが知られています。消化器の食物アレルギーを持つ犬の60%は、排便の回数が1日3回以上になると言われています。アレルギーは体質による病気ですので、1/3〜1/2の症例は1歳未満で発症すると言われています。アレルギー検査を実施したり、数種類の異なるフードを2週間おきに変えていき、症状が改善するかどうかを確認することで診断していきます。
体質の問題であり、治るものではありませんので生涯お付き合いが必要な病気です。
①問診
どの症状が、いつから、どのように進行してきたかを細かく伺います。吐き気であれば1日の中でいつ吐くのか、下痢であればどれくらいの硬さの便が1日に何回出るかなどをお聞きしています。
②検査
当院では吐き気や下痢といった症状が消化管からくるものか、他の臓器からくるものかを判断するために血液検査を実施しています。その他、糞便の検査や超音波検査を実施して、どのような異常が起きているのかを調べていきます。
③治療
症状が軽い場合はご飯を変更したり、少しの間絶食するだけで治ってしまうこともあります。症状が重篤な場合、脱水を起こしていることが多いため、点滴や注射などを行う場合もあります。
外科的な治療が必要な場合は専門の病院をご紹介いたします。麻酔下でのCT画像検査が必要になる場合もあります。
消化器疾患の場合、数日前からの症状などの急性のものであれば、その時の状態に合わせて点滴治療や投薬治療などをしていきます。なるべく薬を使用したくないという場合には、ドイツの自然療法を利用することもあります。
膵炎も何度も繰り返して起こしてしまうコの場合、食事の見直しやドイツの自然療法、オゾン療法を併用することで再発を防ぐ治療をすることもあります。食物アレルギーの場合はフードの見直しをしますが、食物アレルギー用の処方食を食べてくれないコもいます。当院ではそういったコの場合、何が何でも処方食を食べてくださいというのではなく、そのコが食べれそうなもので治療への糸口を見つける手立てをします。具体的には、当院の付属施設である、癒しの杜にて食事のカウンセリングを専門の獣医師にやってもらい定期的に当院で症状のチェックをしていきます。
いずれにせよ、食物アレルギーなどの場合には、生涯に渡る治療が必要となることが殆どですので、飼い主さんとしっかりお話しをさせていただき、どのような治療を希望されるのかによっていくつかの選択肢をお伝えして、相談の上、治療の選択をしております。