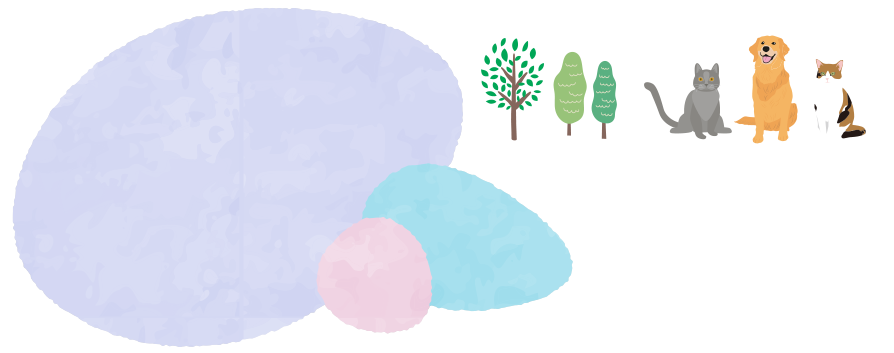
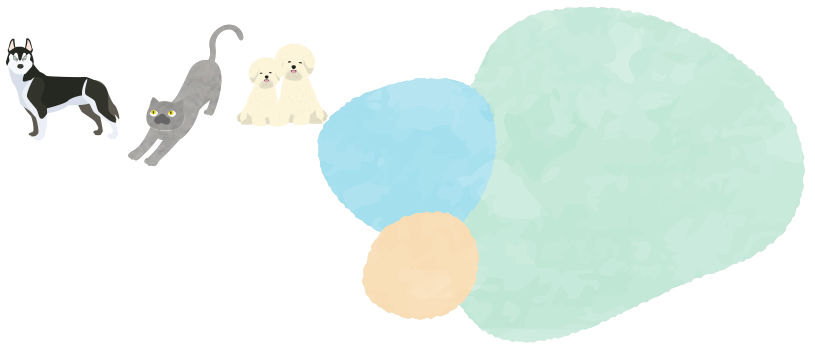

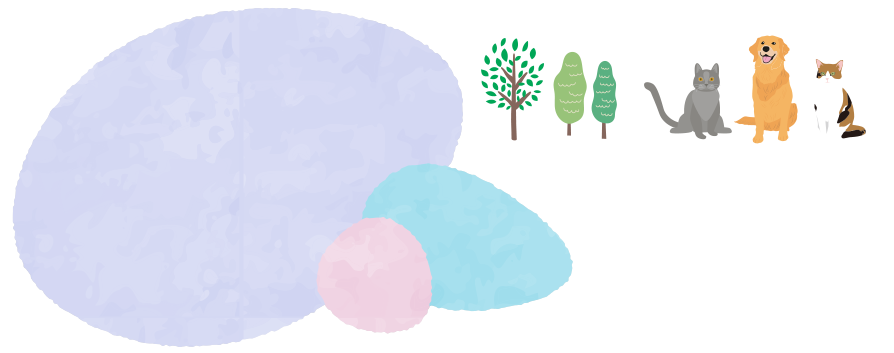
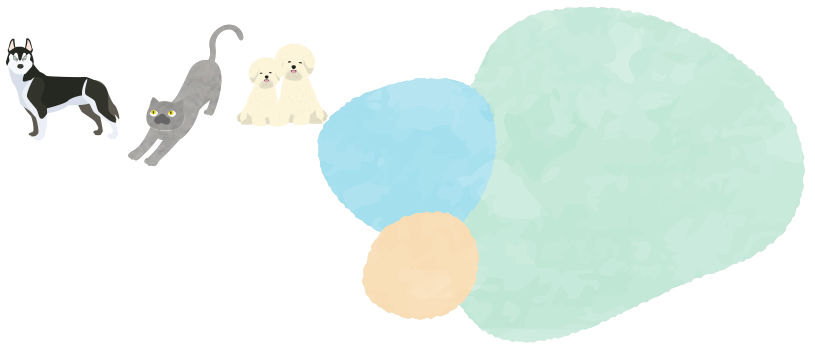

こうご動物病院の腫瘍科について掲載しています。
![]()
・身体にしこりができた
・皮膚がじゅくじゅくしている
・お腹が張ってきた
・ごはんを食べているのに痩せてきた
・口の中が腫れている(ごはんをこぼす、食べづらそうにしている、口が臭う、涎が増えた)
■犬
中高齢犬でよく見られる腫瘍です。犬の乳腺腫瘍の良性と悪性の比率は1:1と言われています。悪性腫瘍の場合は、リンパ節や肺に転移することがあります。治療は基本的には外科的な切除を行います。術前の検査や術後の病理検査で転移が判明した場合は、抗がん剤治療を行うこともあります。
■猫
猫の乳腺腫瘍は、猫の腫瘍の中で3番目に多い病気です。ほとんどが悪性であり、リンパ節や肺に転移することが多いです。猫の乳腺腫瘍は悪性の挙動を示すことが多いため、1つの小さなしこりであっても同じ側の乳腺を全て摘出します。術後の病理検査で転移が判明した場合は、犬と同様に抗がん剤治療を実施することがあります。
犬の皮膚腫瘍では最も発生頻度が高い腫瘍です。肥満細胞腫の形はさまざまで、1つのものから多発するものや、柔らかいものから硬いものまであります。肝臓や脾臓に転移することがあり、食欲不振や元気消失などの症状が出ることがあります。治療は小さいものであれば外科切除と放射線療法が推奨されています。それではコントロールができない場合や、大型のもの、多発しているものについては抗がん剤療法が必要になることもあります。
メラノーマは歯肉に確認されることの多い腫瘍の一つです。皮膚に生じる場合もあります。口腔内のメラノーマは非常に悪性度が高く、さらに転移を起こしやすい性質を持っているため、治療にあたって苦慮することが多くみられます。腫瘍の周囲組織のほか、全身への影響も大きく現れます。例えば顎の骨融解やリンパ節の腫大のほか、肺などにも転移が生じる傾向にあります。さらに食欲不振や体重減少といった“がん性悪液質”を引き起こし、衰弱を招いていき、非常に予後が悪いことが多いです。
治療法としては外科手術が第一に挙げられますが、再発も多いため、外科治療のほか、化学療法(抗がん剤)を併用することがあります。また腫瘍の部位によって放射治療が行われることがあります。
猫の扁平上皮癌は、猫の皮膚腫瘍の11%を占めると言われています。10歳以上の高齢猫で起きやすく、白毛の猫の方が有色の猫よりも発生率が高くなっています。原因は明らかになっていませんが、紫外線の暴露やウイルスの関与の可能性が示されています。治療は可能な限り外科切除を行いますが、腫瘍のできている場所によっては手術が適応とならず、放射線療法や抗がん剤療法を選択する必要があります。
リンパ腫は猫で一番多くみられる悪性腫瘍で、猫の悪性腫瘍の約3割を占めます。猫白血病ウイルスや猫免疫不全ウイルスが関与する場合も多く、お家の外で過ごす経験のある猫ちゃんは要注意の腫瘍です。
消化器に発生するリンパ腫では、食欲不振・下痢・嘔吐・体重減少などの症状や、「食欲はあるが、体重が減って痩せてきた」という症状も認められることがあります。
胸腔内に発生するリンパ腫では、少しの運動ですぐに呼吸が荒くなるなどの症状から発見されることがあります。
①問診
まずはしっかり問診させて頂きます。
どの症状が、いつから、どのように進行してきたかを伺います。しこりの大きさ、色、数なども細かくお伺いします。
②検査
全身の身体検査の他、体の細部まで触診を行い、飼い主様が気付かれていないしこりがないかどうかを確認していきます。
腫瘍の種類を調べるための検査として、細胞診検査を実施します。しこりに針を刺して細胞成分を採取し、どんな種類の腫瘍なのかを調べます。その結果、疑われた腫瘍(種類、悪性度)によって血液検査、レントゲン検査、エコー検査などの追加検査を実施します。
③治療
腫瘍の種類や個数、広がり方によって治療法は様々です。わんちゃんねこちゃんの年齢や体調によってはおすすめ出来ない治療法もありますので、状況に合わせてじっくりご相談させて頂きます。
基本的には腫瘍の転移が起きておらず、取り切れる可能性が高い場合や、取り切れなくても生活の質を維持するために腫瘍を小さくする目的で行うことが多いです。化学療法や放射線を併せて用いることもあります。特に悪性腫瘍の場合は「マージン」と言われる腫瘍周囲の正常組織ごと切除する事で、完治と再発防止を目指します。
いわゆる抗がん剤が主となる治療法です。完治を目指したり、生活の質を向上させるために腫瘍を縮小させる目的などで行います。
腫瘍の種類や体調に併せて薬剤を選択しますが、治療中は副作用が現れる事もあります。常に全身状態をモニタリングしながらの治療を行いますが、体調や検査結果によっては治療を延期する事もあります。
従来の抗がん剤とは違う作用を持つ薬剤で、腫瘍細胞が持つ特定の分子にのみ作用する薬です。特定の種類の腫瘍によっては使用することで効果が認められます。従来の抗がん剤は正常細胞もダメージを受けてしまう事で重篤な副作用が出てしまいますが、分子標的薬はターゲットが腫瘍細胞のみになるため副作用が少なくて済むといわれています。
特定の種類の腫瘍に対して大きな効果を発揮します。また、手術で取り切れなかった腫瘍細胞に対して使用することもあります。放射線治療には特別な施設と知識が必要となるため、お近くの大学病院をご紹介させていただいております。
当院では抗がん剤を使用しない特殊な治療もご紹介しています。お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら