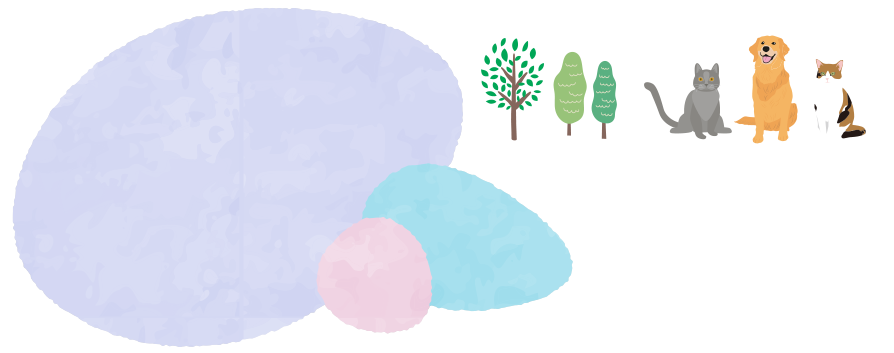
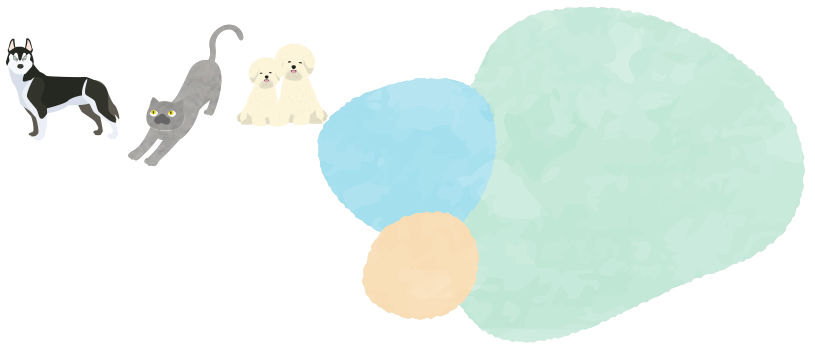

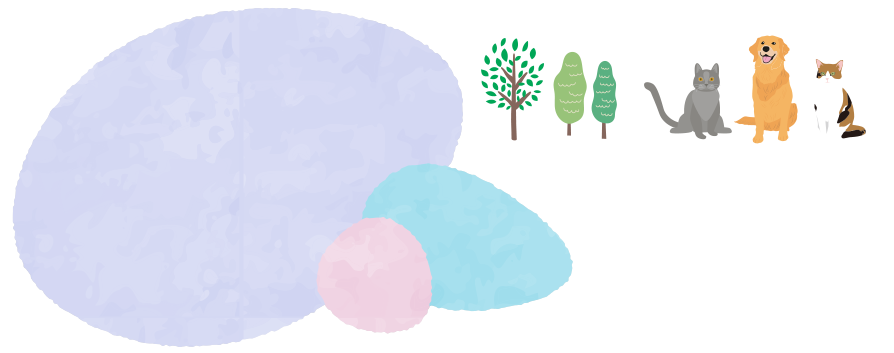
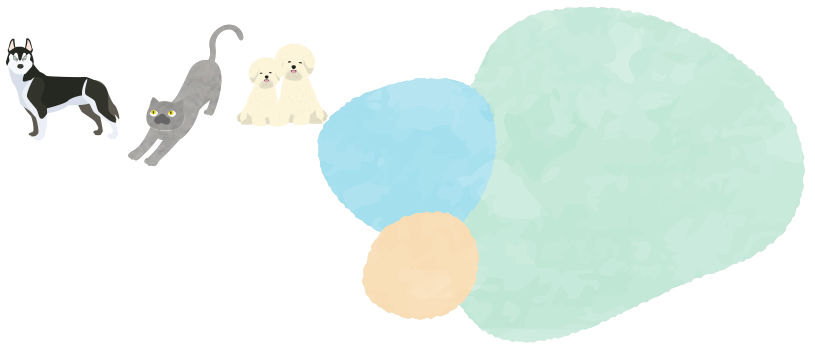

こうご動物病院の泌尿器科について掲載しています。
![]()
・頻尿
・尿が赤い、茶色い
・尿が臭う
・トイレに行くのに尿が出ない、尿の量が少ない
■膀胱炎
膀胱炎は頻尿や血尿を特徴とします。膀胱内の細菌感染や尿石による刺激で膀胱の粘膜が厚くなり、膀胱が大きく膨らむことができなくなります。そのため、膀胱内に尿を貯めておけなくなり、頻尿となります。尿中の感染がある場合は抗生剤での治療が必要です。膀胱の奇形や尿石、腫瘍が原因で治療が難航することもあり、その場合は外科的な治療が必要となることもあります。
■結石症
膀胱炎の原因になったり、腎臓や膀胱で形成された尿石が尿管や尿道に移動して、尿の出口を塞ぐことで急性腎不全の原因になることがあります。結石の成分にはいくつか種類があり、療法食での治療で溶ける結石もありますが、基本的には手術で摘出する必要があります。術後はフードの変更やサプリメントを用いることで尿石の形成を予防し、病気の進行を防ぎます。
■慢性腎臓病
年齢と共に腎機能が低下することで発症する病気です。血液検査や超音波検査を行い、腎臓の機能を評価していきます。健康でも健診などでの定期チェックがおすすめです。病態やステージによってはフードの変更が推奨されたり、血圧の上昇や腎臓からのタンパク質の漏れがみられたときは内服薬を処方することもあります。腎臓の数値が悪化して、脱水が進行すると体の水分が維持できなくなり、点滴が必要になることもあります。
進行性の病気であり、治ることがない病気のため、病気のステージと症状に合った検査と治療が生涯必要となります。
■特発性膀胱炎
特発性膀胱炎は猫の下部尿路疾患の60%を占めていると言われています。ストレスが関与していると考えられており、生活環境の改善が必要となることがあります。また、サプリメントやフードの変更を行い、心を落ち着かせてあげることで症状が緩和することがあります。
①問診
泌尿器系の病気では、水を飲む量や尿の量、回数に変化が出ることがあるため、ご自宅でのご様子を伺います。元気や食欲など一般状態も併せて確認させていただきます。
②検査
一般身体検査、血液検査、レントゲン検査、超音波検査を行い、治療前の腎臓と膀胱の評価をします。
また他臓器にも影響が出ていないか、合わせて確認をします。
尿検査も行うことでおしっこの状態を詳しくチェックします。
③治療
それぞれの病気や症状に応じて必要な治療を提案させて頂きます。内服薬を使用したり、食事内容を変更したり、皮下点滴を行うこともあります。
結石が原因の場合は外科治療が推奨されることが多いです。外科的な治療には専門の設備が必要とされるため、手術ができる病院は限られています。ご希望の飼い主様には泌尿器専門の病院をご紹介いたします。
④定期的なモニタリング
腎臓や膀胱の疾患は、初期であればご飯を変更することで対応できる場合があります。症状が重度になると集中内科治療や外科手術が必要になることもあります。完治する病気もありますが、再発したり、生涯お付き合いする必要がある場合もあります。その場合は退院後・術後のケアを一緒に相談しながら頑張っていきましょう。
特発性膀胱炎や尿石症などの場合、一般的には処方食を使用して治療をすることが多いのですが、処方食が食べれないコもいます。当院ではそういったコの場合、何が何でも処方食を食べてくださいというのではなく、そのコが食べれそうなもので治療への糸口を見つける手立てをします。具体的には、当院の付属施設である、癒しの杜にて食事のカウンセリングを専門の獣医師にやってもらい定期的に当院で症状のチェックをしていきます。
またストレスが関与するような特発性膀胱炎の場合には、メンタルを落ち着かせるサプリメントや漢方、ホメオパシー、そのコにあったバッチフラワーレメディなどを処方することで症状の緩和を図ることもあります。
慢性腎臓病の場合、一般的な点滴治療とともにドイツの自然療法のホモトキシコロジーやオゾン療法を併用しての治療をすることが多いです。ホモトキシコロジーやオゾン療法を使用しての治療の場合、一般的な西洋医学のみの治療よりもQOLの向上や場合によっては数値の改善がみられることもあります。病院での点滴治療がストレスになる場合には、飼い主さんにやり方をお伝えしてお家でやってもらい通院は最低限にしていくこともあります。
いずれにせよ、慢性的な病気の場合には、飼い主さんとしっかりお話しをさせていただき、どのような治療を希望されるのかによっていくつかの選択肢をお伝えして、相談の上、治療の選択をしております。